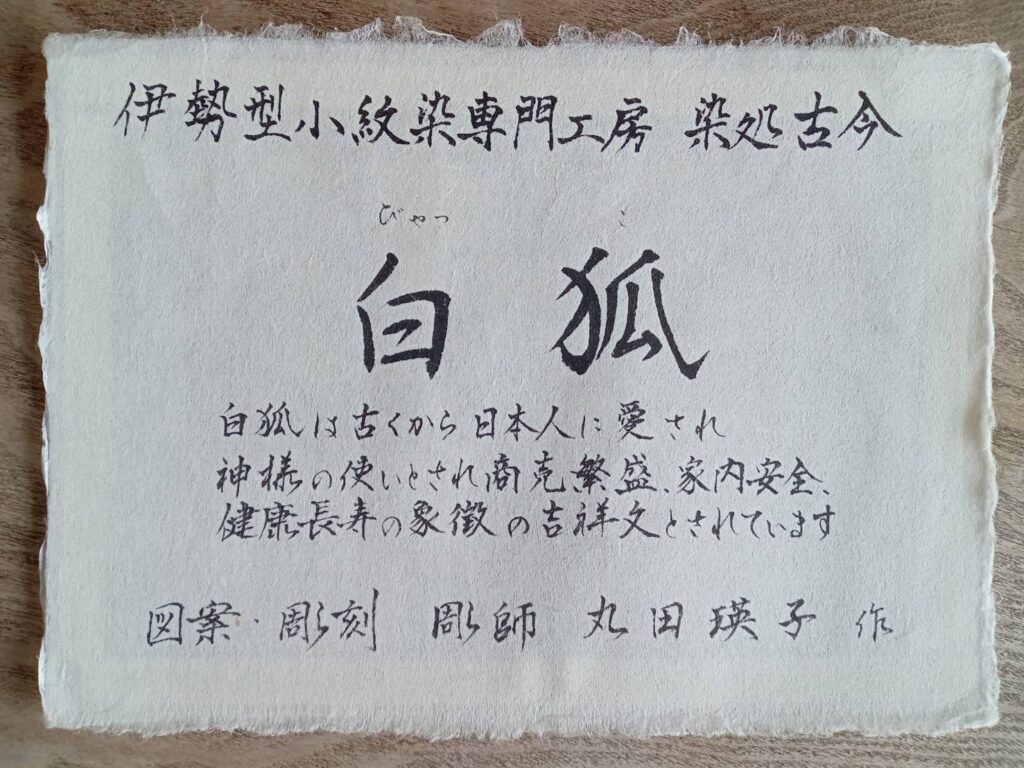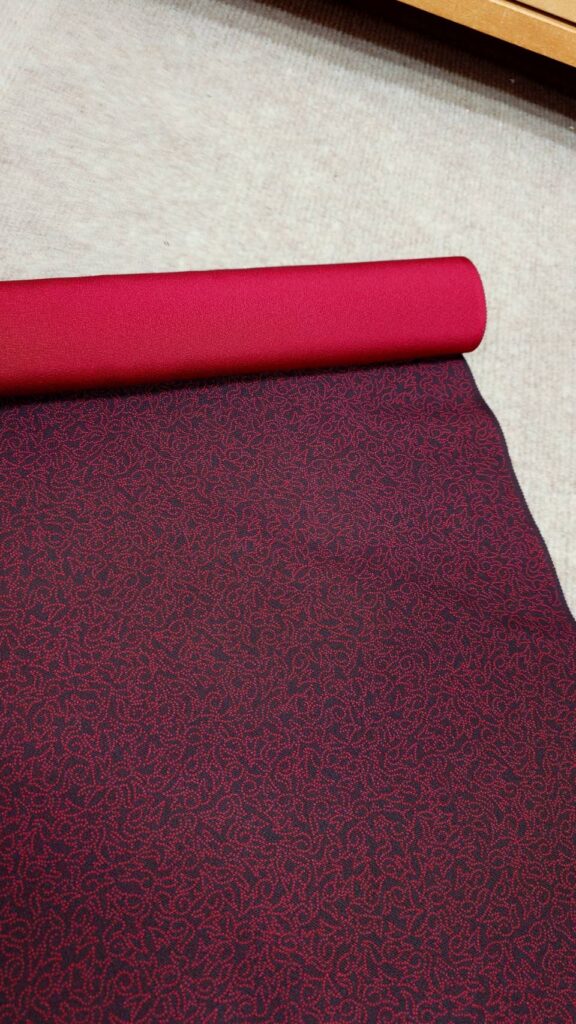みなさん、こんにちは。
京都の7月は祇園祭で賑わいます。
祇園祭の鉾町は、もともとは呉服の問屋さん街です。
今はもうやってない所が多いですが・・・
鉾が立つと、室町には配達できないので
昔から休業する会社が多かったのです。
古今では、その期間を利用して、板洗いをします。
まず、前日から、板に水をかけて、糊をふやかします。

ひたすらゴシゴシゴシゴシ
糊を落とすために、ゴシゴシゴシゴシ
一年間頑張ってくれた、板に感謝の気持ちを込めて・・・
ひたすら、餅糊を落としていきます。


糊を落とし終えたら、三日間陰干しをします。
乾ききったら、また板に餅糊を塗って乾かします。
大切な古今の年間行事は、祇園祭の頃に毎年行います。
このような事をやっている工房は、まだあるのでしょうか?